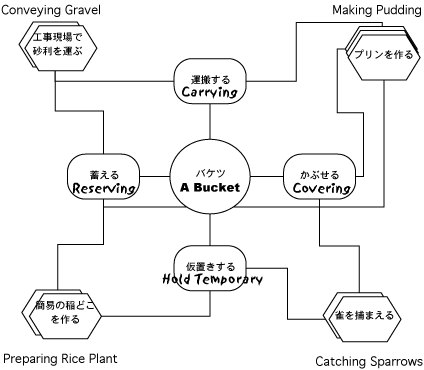セベラルネスと層組−都市連鎖詠みのための拡張キーワード ここでは、先にあげた引用ノートを基本にしつつ、都市連鎖詠みのための拡張概念を提案する。その拡張性は、特に、事物の時間的変容を可能にするメカニズム解読とその実体的拡張(デザイン)に関するためのものである。
●キーワード10 層組(そうそ、そうぐみ)
各時代の都市パターンの受け継ぎ方の組み合わせによって生じたバリエーション。
セウ゛ェラルネスを基本にすえ、都市連鎖のメカニズムを考えていくと、そのバリエーションの総体はどのように整理することができるだろうか。
するとそのための基準に値する筆頭は、まず「コンテクスト−かたち」の軸である。つまり都市転用の主体が、都市のコンテクストを受け継ぐか、あるいはかたちを受け継ぐかによって発生する割合のレンジである。もうひとつはその受け継ぎ方が都市のどのようなスケールを相手にしているかである。これは端的に「部分−全体」という幅で考えることができる。
そのバリエーションは、いずれにせよ都市転用者による都市《詠み》の技法の諸相を映し出すであろう。意識的にモニュメントのみを残す、知らぬ間に地割りを受け継いでいる等…。そのバリエーションが、「枕詞」「序詞」「掛詞」「縁語」「本歌取り」「歌枕」「見立て」「物名」「体言止め」等といった和歌詠みの技法に類似していると思われる理由は、双方がなんらかの編集を先行物に対して行うからである。(図E 都市連鎖詠みの技法空間、和歌の技法それぞれについてはそこで説明)
いずれにせよ先の二つの軸の交差によって《詠み》の技法空間をとらえた場合、その手法はセベラルである。しかしながら、都市の連鎖はその有限の《詠み》を、各時代ごとの複数回、選択的に行うことによって、豊富な展開を示した。つまりそれは可能性の乗算的増加をもたらすのである(連鎖都市年表参照)。これら各時代ごとの詠みの技法の複数回の組み合わせによって現在の都市の部分部分は個別的な性格を持つ。このプロセスが層組である。
名著『日本の都市空間』では、伝統的都市空間のパターン解析を巧妙な命名によって魅力あるものにしている(例:布石・あられ・したがえる、など)。しかしながらそれはできあがったかたちのみを問題にしていた。私たちはむしろ詠み方の選択パターンによって、都市の姿を区分しようとしているのである。(中谷)
『都市は連鎖する』Top Page